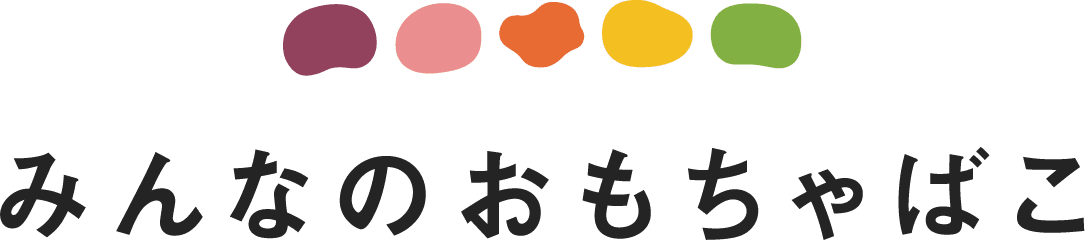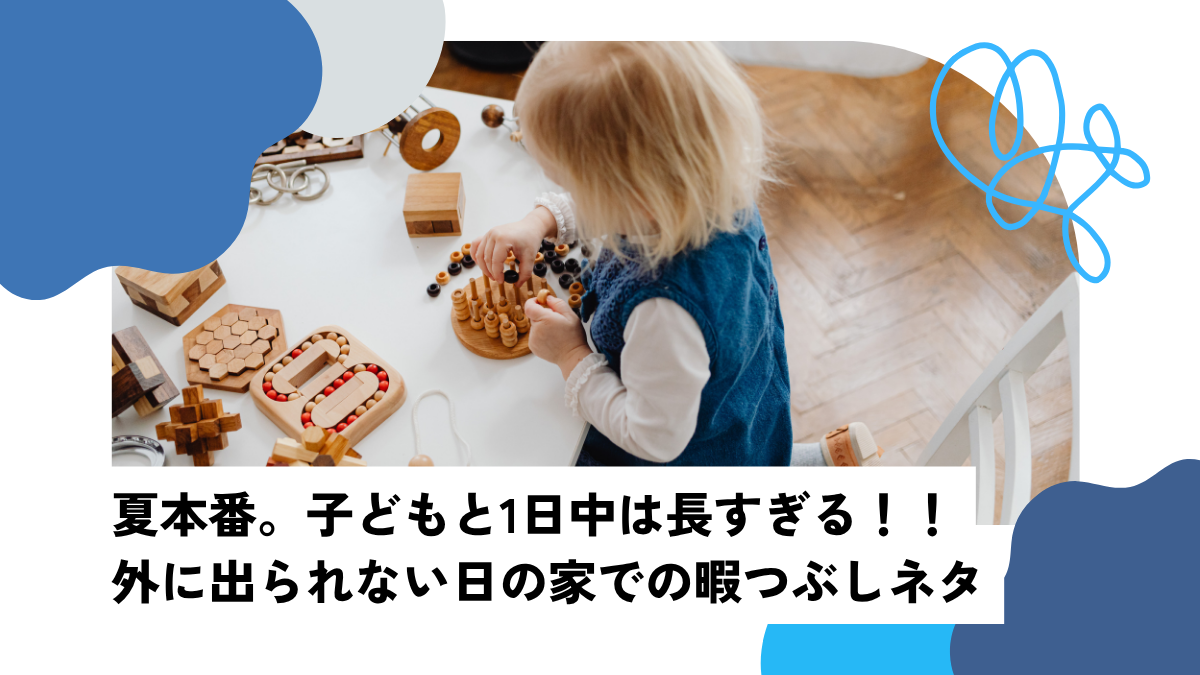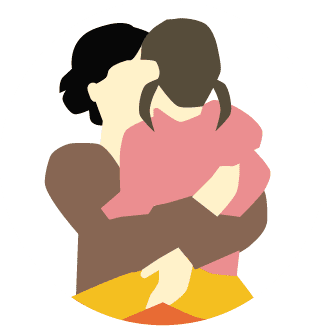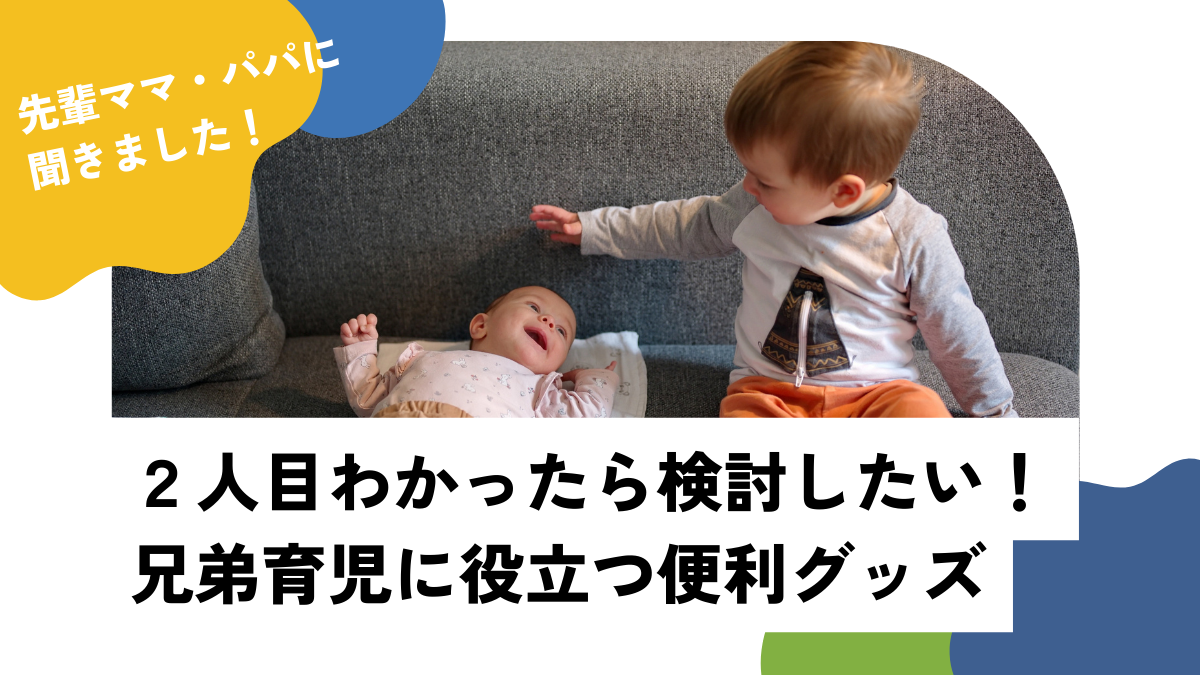子どもがYouTubeばかり見ている……
かなり厳格なおうち以外は多くの家庭で悩みのタネになっているのではないでしょうか。
なかなかやめられず、「もう、おしまい!」「イヤだー」を何回も繰り返し、イライラを募らせるなんてこともあるのではないかと思います。
我が家でもそんな日はありますが、だいぶコントロールできるようになってきたので、これまでにかき集めてきた知識や情報と、実践から編み出したルールをご紹介します。
「ネットで動画」の何が悪いのか
子どもに対するネットの影響を考えるとき、子どもが赤ちゃんなのか、小学生なのか、中高生なのかで、問題や適切な利用方法が大きく変わってきます。
医療系・保育系・教育系の情報をかき集めていくと、赤ちゃん〜幼児の場合の問題点はだいたい4つでした。
問題①視力への悪影響
小さい子は視力が発達していく途中です。そんな時期に近くばかり見ていると遠近調節や立体視などのメカニズムに影響があります。
スマホやタブレットがよくないのは画面が小さいから。狭い範囲に一点集中になるのがよくないということで、ブルーライトはあんまり関係ありません。
参考:
たまひよ「視力がどんどん成長する乳幼児期。「スマホを見せるのは絶対にダメなの?」「どうつき合うといいの?」目の専門家に聞きました」
公益社団法人日本眼科医会「小児のブルーライトカット眼鏡装用に対する慎重意見」
回避方法①デバイスはなるべく大きく、視聴時間を制限する
どうせ見るならスマホよりはタブレット、タブレットよりはパソコン、パソコンよりは大きいモニターを選びます。
また長い時間見るのがよくないので、15分などで時間を区切って、目を休めること。遠くや緑のものを見るように促します。

また、目だけの問題を考えるなら、映像をやめて音声にすれば問題はないということになります。赤ちゃんを泣き止ませたい時など、音だけでも用が足せるなら絵を見せないという回避策もあります。
問題②言語発達やコミュニケーションへの影響
頭が悪くなると言われるのは主に言語発達への影響です。視聴時間が長くなると親子の会話が減り、その結果、コミュニケーション能力が磨かれなくなるそうです。無言で動画を見ているだけだと、言葉のやりとりを通じて学ぶ機会が奪われてしまうのです。
本来だったら使っていた脳みそが使われなくなるのが問題で、スマホやパソコンからなにか悪いモノがでているということではありません。
参考:
Newsweek「2歳未満の子供でも1日平均42分…スクリーンタイムを制限すべきこれだけの理由」ほか
回避方法②子ども向けコンテンツを選び、意識的に会話を増やす
会話がない状態にならなければいいので、コンテンツをきっかけにコミュニケーションをとりましょう。
たとえば、映像を見ている時に話すとか、終わった後に感想を聞くとかいったことをしていけば、受け答えの練習にもなり得ます。

たとえば、「⚪︎⚪︎マン、かっこよかったね〜」「⚪︎⚪︎ちゃんはどっちが好きだった?」など、映画を見終わった後にお茶しに行った時のテンションで話してみるのはどうでしょう?
コンテンツを探す時はYouTubeキッズやディズニープラスなど、子ども向けのものが集まってるところで探すのがおすすめです。子どもの情報量や理解度に合わせているので、見たことを話すのもやりやすいと思います。
映像の時間も短いものが見つかるので、「これを見たらおしまい」の区切りもつけやすくなります。
問題③身体の発達への悪影響
動画やスマホを見続けていると、長時間座って体を動かないことになります。これは見ているのがYouTubeであろうが、テレビであろうが、同じような問題がおこります。
回避方法③視聴時間を制限し、運動を意識的に増やす
体を動かす時間を減らさなければいいので、見る時間を制限して、運動を増やせばいいということになります。なかなか時間が減らせなければ、見るものをダンスや体操の映像にして、一緒に体を動かしてみるのはどうでしょう?
問題④生活リズムの乱れの原因に
ブルーライトは目が悪くなるというよりも、眠りの質を悪くするという点で問題です。
夜に見ると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりして、生活リズムが崩れやすくなります。
体内時計もこれからしっかり整えていけないといかない時期なので、夜のスクリーンタイムはできるだけ避けた方がよいです。
回避方法④夜はできれば見ない
寝る前はできれば見ないことです。
スマホの場合はおやすみモードを設定しておくと白黒になり、寝る時間だというのが分かりやすくなります。
小さい子どもが動画を見続ける問題点と回避策まとめ
①視機能の発達に影響→デバイスはなるべく大きく、休憩をとって見続けない
②言葉の習得が遅れる→子ども向けコンテンツを選び、会話のきっかけにする
③身体の発達に影響→視聴時間をおさえて、運動を増やす
④生活リズムの乱れ→寝る前は見ないようにする
2〜3歳を過ぎれば人間の体としての機能もだいぶ整ってきて、言葉なども出てくるので、赤ちゃん〜乳児より制限は緩やかでよく、小学生を過ぎれば学校でもタブレットを使うので、逆にうまく活用していく方向がよいのではないかと思います。
幼児&小学生(低学年)のYouTube視聴ルールの一例
低年齢の頃はまだ反抗はしても圧倒的な差があって、大人がやめさせようという意思を持っていれば多少、強引に終わらせることもできていました。
でも、成長して口が達者になってくると、YouTubeを見たい子どもと見せたくない親の戦いに。こうなると、根負けして見せてしまうか、怒って取り上げるかという結末になりがちです。
できれば毎日のバトルは避けたいと思って、いろいろと試した結果、我が家では現在こんな仕組みで落ち着いています。
(1)使い切りチケット制
時間で区切ると動画がキリ良く終わらないこともあるので、回数で決めています。
ただ、動画に没頭しているうちに子どもが後何回見られるのかを忘れてしまい、もっと見たくなってしまうので、回数が目に見えてわかるように、A4の紙に手書きで券をつくりました。
券がなくなったら今日の分はおしまいというのが目で見て分かるので、「まだ見たい」と駄々をこねていても、頭のどこかではもう見れる可能性は低いというのを感じているのではないかと思います。
ポイント:原則的に繰り越し禁止。例外は理由必須
頭のなかで色々と考えられないのを補助するためにチケットという目に見える形にしているので、翌日に繰り越す、短い動画は1枚で2回見られるのような複雑なルールは基本的になしにしています。
子どもの抗議に耐えかねて、その場しのぎの例外的な運用をすると、結局なし崩し的に何でもアリになっていき、収拾がつかなくなります。ルールは決めたら変えないのがポイント。予定が違うなどで特別な理由がある場合には、今日はこういう理由だから枚数が変わるのだということを説明しています。
(2)再生リストとYouTube premiumを活用
動画のは5〜6分までの長さの動画に限定しています。
それを再生リストにまとめて、この中はどれを見てもいいという状態にしました。
20分の動画や1時間の動画が混じっている一覧を見せて、選んでもいいものを口頭で伝える方式だとトラブルになったからです。気になるサムネイルを見てしまったら、どうしても中を見たくなってしまうという心情は理解できるので、選べないものは見えないようにしました。
また、実家がYouTube premiumをやっていたため、ファミリープランに入れてもらい、広告も入らないようにしています。
ポイント:前後編などのコンテンツはなるべく除外
前編、後編などと分かれている動画は前編を見たら当然、続きが気になるので、やめられません。でも券の枚数は決めているので、ちょっと手間ではありますが、1つで完結する動画を中心に選んでいます。
この方法でもグダグダになる日はありますが、ルールがあるおかげで言い聞かせやすくなりました。
夕飯後に30分ぐらい、朝はなかなか起きてこない日に目覚まし代わりに10分ぐらい、休日はもう少し長くなることもありますが、1日トータルで長い日でも2時間は超えない範囲におさまっています。
動画の見過ぎでイライラしないためのポイント3つ
①「ルール決め」より「ルール説明」を重視
「各家庭で話し合ってルールを決めましょう」とだいたい何にでも書いてありますが、大事なのは良いルールを決めることより、いかに守ってもらうかだと思います。
「勝手に決めると守らないので子どもと話し合いましょう」と書いてあることも多いですが、完全ゼロペースから子どもと決めるのは難しいです。おすすめは先に大人が1日30分まで、夜20時までなどとざっくり決めてやってみた上で、「もっと見たい」「この時間にみたい」など子どもの要望に応じて微調整をするやり方。
見たりなくて文句を言っている時に何が嫌なのかを細かく聞いていくと、「短いのをたくさん見るより長いのを1個みたい」「お姉ちゃんが勝手に決めたから自分は別のが見たかった」など理由がわかってきます。それに沿って「時々休憩するならいいよ」「じゃあ、1回ずつみよう」など新ルールをつくると納得感が得やすいです。
ルールを調整する時に「おめめによくないから」「寝る支度が終わらなくて明日起きられないから」など理由を説明すれば、大人の都合で言っているのではないことを理解してもらうこともできます。
②動画を見たくなるタイミングをおさえる
子どもが動画を見たがるタイミングというのがあります。
たとえば、一通りやりたいことをやって手持ち無沙汰になった時、動きたくないけど寝たくもない時、めちゃくちゃ面白くて気に入っている動画のことを思い出した時など。
いったん見始めるとやめるのが大変なので、このポイントをおさえて、「動画を見たい」と言い出したら似ている別のことに気を逸らすといいです。
何かまったりしたい時であれば「絵本を読もうか?」など静かな遊びを提案してみたり、色々やって飽きて刺激がほしい時であれば、「そろそろ3時だから、おやつを買いに行こうよ」「新しいシールがあるけど、やる?」など、気分の変わることを提案してみたり。
あとは子どもが何か面白いことないかなぁと室内を見まわした時に、動画を見るときに使うパソコンやスマホ、動画を見るときのお部屋などが目に入ると、YouTubeを連想しやすくなります。思い出すきっかけを極力へらせば「動画をみたい」と言い出す頻度が減らせる可能性があります。
③イライラの感情を分解する
子どもが動画を見すぎるからイライラするのですが、子どもを変えようとしてもバトルの回数はなかなか減らせません。なので、自分側にあるイライラの原因を考えてみるというのもいいです。
落ち着いて気持ちを書き出してみると、疲労や罪悪感、心配や恐れなどが隠れていることがあります。
たとえば、単純に生理前、寝不足、仕事の山場など、他の理由でイライラしやすくなっているなら、そちらの対処に集中してみるのもいいかもしれません。
また、突きつめてみると「私のせいで子どもがバカになったらどうしよう」「楽ばっかりして母親としてちゃんとしていないと思われないか」など、無意識のうちにちょっとこじれた考え方になってしまっている時もあります。
そういう時はメンタルを整えるチャンスです。親として自分ががんばってきたことを数え上げて自分を認めてあげたり、子どもがちゃんとできていることに目を向けて子どもの幸せについて考えてみたり。「ルールを守らないのが許せない」という時は、小さな子どもが一発でルールを守れるわけがない、今は練習中なんだと捉えてみたり。
動画を見すぎて死ぬことはないので、ゆっくりやっていけば大丈夫です。
夏休みやワンオペの日などに使える動画以外の選択肢
長い休みにダラダラと見てしまう時は予定をつくりましょう。
長期休暇は子ども向けの体験教室などが多くあります。市区町村のホームページで調べればプール教室など比較的リーズナブルなものが見つかります。いこーよなどのお出かけ情報サイトでイベントを探してみるのもいいかもしれません。
予約のいらないプールや児童館、図書館などで、まとまった時間を過ごせれば、動画を見る時間も減らせます。
また、友達と約束して遊ぶなど、人と会う予定をつくるのもいいですね。ベビーシッターさんも、外に遊びに連れ出してもらうことができる場合があります。
ワンオペの日は少ないのであれば、そういう日は動画に頼るのもしかたないと割り切ってもいいかもしれません。毎日YouTubeに頼ってしまうようであれば、たとえば、こんなサービスもありますよ。
開始直前まで予約可能なので都合にあわせて使いやすいです。
おもちゃのサブスクも年齢にあった新しいおもちゃを出すと集中してくれるので、おすすめです。