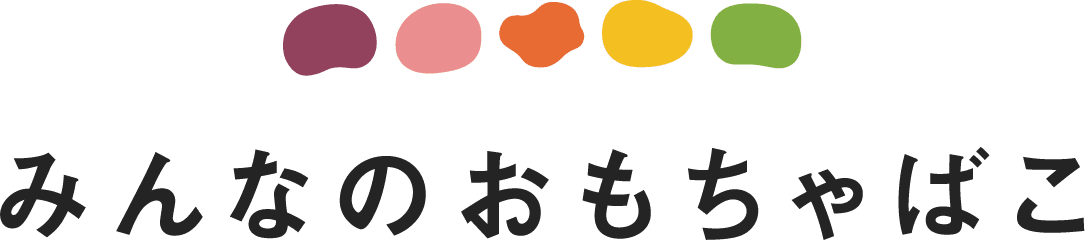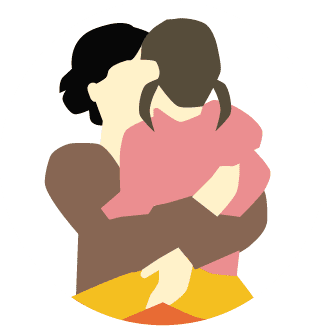赤ちゃんから幼児にかけては、体も心も頭も急成長する時期です。それに伴って、興味の対象もどんどん変わっていくので、遊び方も月齢や年齢によって、かなり変わります。
0歳から3歳までに分けて、その様子を少し詳しくみてみましょう。
<0歳>成長スピードが尋常じゃない
1ヶ月で全く別人になったかのように急速な成長を見せる0歳児。
新生児は睡眠も授乳も排泄も間隔がとても短いです。徐々にまとまって寝られるようになり、朝と夜の区別がついていくようになります。
嗅覚や聴覚は発達が早いですが、視力は発達が遅く、あまり見えていません。色もよく分からないので、絵本やおもちゃは赤など、ハッキリした色合いのものに興味を持ちます。
最初は寝返りもできずに天井の方を向いて寝ているだけですが、まず寝返りができ、ずりばいやお座りをするようになり、ハイハイをして移動ができるようになっていきます。
自分で体の動かし方がわかっていない時期に興味を示すのは、ベッドメリーのような「見る」おもちゃや、どう動かしても音が鳴るガラガラのようなおもちゃです。
体の動かし方がわかってくると、周りのモノに興味が出てきます。これは何だろう?という好奇心から触ったり叩いたり投げたり舐めたり。起き上がりこぼしのように、自分が働きかけると必ず同じ反応を返してくるモノに熱中します。
生まれて間もない時期は起きている時間も短く、だいたい泣いてるか飲んでいるかオムツを変えているかなので、遊ぶという感じではないですが、生後半年を過ぎてくると、おもちゃで遊ぶような時間もできてくるでしょう。
「ベビー」のタグがついた記事では、この時期の赤ちゃんがよくするイタズラや、赤ちゃんにおすすめのおもちゃについて紹介しています。
<1歳>自分で歩きはじめる
1歳の大きなイベントといえば「歩く」ことでしょう。1歳前ぐらいからつかまり立ちを始め、つたい歩き、1人歩きと成長していきます。歩くようになるので、ファーストシューズが必要になりますね。この頃には、オムツもほとんどの赤ちゃんがテープタイプではなくパンツタイプになっているでしょう。
ハッキリした言葉ではないけれど、コミュニケーションをとろうとする様子も出てきます。「ちょうだい」「どうぞ」などのやり取りもできるようになり、子育てがちょっと楽しくなってくるタイミングもあるのではないでしょうか。
0歳と比べれば、かなり達者に動き回りますが、それでも細かい動きはまだ難しいです。フタをあける、ボタンを押すなどの力加減が必要な動作は大変なので、おもちゃも大きめの積み木やブロックのようなシンプルなものがおすすめ。
外で他の子と触れる機会も出てくると周りの子との違いも見え、おもちゃでの遊びかたなどを通して少しずつ子どもの個性も見えてくるかもしれません。
<2歳>自己主張が強くなる
俗に「イヤイヤ期」といわれ、主張が強くなる時期。今までなされるがままだった子どもが、段々と意思を持ち始めます。言葉も文章に近づいてきますが、まだ上手に伝えられず「イヤイヤ」になってしまいます。
自分でやりたいので勝手に進めたり手伝ったりすると怒りますが、自分でやってみてうまくいかないとそれはそれで不機嫌になるので子育てに苦労する時期です。
とはいえ、体もかなりしっかりしてくるので、公園に出掛けてすべり台などの遊具で遊ぶ時も、ちょっと離れて見ている余裕もでてきます。「向き」や「順番」などもわかるようになり、手先もだいぶ器用になってきます。赤ちゃん感がだいぶ抜けてくる感じとでもいいましょうか。
遊べるおもちゃも、ひらがなや数字などに触れたり、生活習慣について学んだりするような知育玩具に触れるようになっていきます。
<3歳>友達と遊ぶようになる
言葉や食事もだいぶ達者になり、トイトレも進む子が多い3歳。自分のことがだいぶできるようになってきて、周りの子への興味も強まり、相性のよい友達と遊ぶようなシーンも増えてきます。服装や行動などでの男女差もかなりハッキリしてくる印象です。
また、3歳ともなればずっと家で過ごしていた子も、幼稚園に入園するなど集団生活を経験する機会が多くなってきます。他の子と過ごす時間が増えれば、おままごと的な遊びも増えていきます。
サンタクロースがくる「クリスマス」や、1つ年齢があがり皆にお祝いしてもらえる「お誕生日」などの行事についても段々わかってきます。アニメや絵本などのお話も、それまでに比べると、だいぶ長いストーリーや複雑な話についてこられるようになっているでしょう。
ルールがある遊びなどはまだ難しいこともありますが、遊べるおもちゃの幅はかなり広がってきます。
小さい子は遊びながら学んでいる
体や心、知能が発達していくのには段階があって、一足飛びにはいきません。ハイハイの次にいきなり走ったりはしませんし、ミルクから離乳食を経ずに、幼児食にすることもできません。そして、段階を追って成長していく過程で、大事なのが遊びの時間です。
そのため、おもちゃも今できることに合わせて選ぶのがポイントです。早期教育のようなつもりで少し先取りしても成長が早まったりはしません。
発達には個人差もあります。成長のスピードが子どもによって違うのはもちろん、成長のしかたも様々です。
また、子どもは遊びながら、いろんなことを学んでいます。モノが下に落ちるというような物理的なことも、マジックテープやボタンのような生活動作的なことも、人を叩いてはいけないというようなことも全部です。
小さい子なんかは起きている時間はずっと遊びと言っても過言ではないかもしれません。ご飯の時もお腹がいっぱいになったら遊んでいますし、お風呂の中でも遊んでいます。
そのため、おもちゃも大人が想定するような使い方をしないことは多いです。バケツを頭にかぶってみる、といったようなことをします。バケツはすくったり運んだりするものですが、子どもの発想ではそうではないのです。
3歳、4歳になってくると、だいぶ「遊び」と「学び」が分かれてきますが、そこまでは「遊び」と「学び」はほぼ同じようなもの。おもちゃがなければ遊べないということはなく、何もなければ自分で遊びを生み出します。
子どもが集中して何かをしている時は危険でなければそっとしておいてあげると、きっと大きな学びを得られます。
「正しい遊び方」や「理想的なおもちゃ」というのはないのですが、こういった子どもの特性を踏まえると、年齢に合ったおもちゃ選びや子どもの興味を引き出す遊びかたなどはあります。難しいと思ったらプロに相談するのもいいかもしれません。このサイトでは、幼児から赤ちゃんの間に便利なサービスとして「おもちゃのサブスク」をおすすめしています。
参考「コミュニケーションに関連する子どもの発達過程」https://www.kango-roo.com/learning/9898 ほか